稲作の歴史
稲作のはじまり
南房総で稲作の開始を物語る資料は、いくつかあります。
館山市笠名から出土したと云われる石包丁は、 千葉県内唯一の弥生時代の形態を示す資料です。
鴨川市根方上ノ芝条里跡からは今から約1800年~2000年前の 弥生時代後期の水田を伴う集落跡が発見されています。 また、ここでは砂岩製の穂摘み具と推定される石器も出土しています。
このころの水田は、館山市長須賀条里制遺跡で検出されているように 小区画水田といって、一枚の面積が1~3㎡程度に非常に狭く畔で区画されたものでした。 水田面を造成するには、斜面に対して水平な面を作り、水を回すために畔と段差を 付けながら区画していかなければなりませんので、小さな労働力に応じた造成方法が 小区画水田だったのではないでしょうか。この水田造成方法は、棚田にも通じる方法です。
古墳時代に入ると、同じく館山市長須賀条里制遺跡で用水路と水田が発見されています。 水路から畦畔越しに水を入れるために木樋というU字溝を埋設し、灌漑施設が整った水田の 姿がうかがえます。しかも、埋設された木樋の蓋には、倉庫の扉を転用して使用していました。
条里
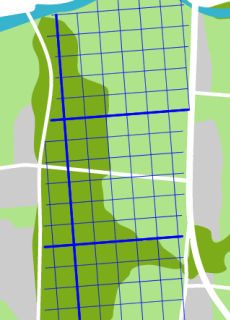
条里制とは、古代における班田収受法を施行するための土地区画制度です。 律令国家は、公地公民制の下で、民衆に水田を貸与し、税を徴収するために、 土地を碁盤目上に区画することで地番を付し、課税台帳を作成しました。
この碁盤目上の条里区画は、後々まで土地区画の基本として踏襲され、 現在でも条里型の水田区画が残っている場所があります。
条里の基本的区画は、一辺約654mの碁盤目の中に約109m四方の坪が 36づつ入ります。これで、基点から縦方向に一条・二条・・・、 横方向に一里・二里・・・というように付し、この組み合わせで一条二里というように 654m四方が特定できます。この単位を里と呼びます。さらに、里の中を 1~36の坪が付されていますので、一条二里三の坪というような呼び方で 109m四方の場所が特定できるわけです。
実際の水田は、109m四方の坪の中が長地型、半折型という区画で 10等分されています。
安房地域での条里区画は、比較的広い平野部を持つ館山平野(館山市~三芳)、 長挟平野(鴨川市)にみられ、それぞれ古代の安房郡、 長挟郡に条里の展開していた様子が偲ばれます。
棚田

「大山千枚田」を代表とする南房総の棚田は、すばらしい景観を見せてくれます。 しかし、この景観は、自然にできあがったものではなく歴史的な必然性の下で先人たちが、 つくりあげた人工的な景観です。
棚田が形成された歴史的な経緯は、あまりよくわかっていません。 平野部ではなく、水田として適さないと思われる斜面地までも水田を造成しなければ ならなくなった社会的背景とは何だったのでしょうか。
大山千枚田についてもいつ頃できたものなのか、よくわかりませんが、 おそらく江戸時代につくられたものだと推定されています。 人口増加による食糧の増産や年貢の増大に対処するための耕地の拡大が考えられますが、 これからの調査・研究が期待されるところです。
